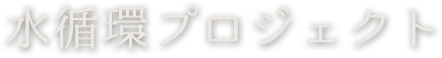水の環でつなげる南の島のくらしプロジェクト
1.南の島での水にまつわるいろいろな問題
沖縄の島じまでは,近年の居住・観光人口の増加に伴って土地利用が進み,地下⽔や湧き水の塩⽔化・枯渇化,飲み水用水源の⽔質悪化,農業用水や観光⽤水の不⾜,水質悪化による生き物や農作物への悪影響など,さまざまな問題が起きてきています。
- 地下⽔・湧き水の塩⽔化や枯渇
- 飲み水用水源の⽔質悪化
- 農業用水・観光⽤水の不⾜
- 水質悪化による生き物や農作物への悪影響
- ⽔に対する意識の薄れ

2.「水の環でつなげる南の島のくらし」プロジェクト発足の経緯
これらの問題の解決には,南の島に特有の⽔の流れ(水循環)を科学的に把握すること,⼈間活動が環境に与えている影響をやわらげるための技術開発をすることが重要です。さらに,これらのことに加えて,きれいな水を使い続けることができる社会をつくるためには,地域のみなさんとともに水との関わり方を見つめ直すことが欠かせません。
琉球大学では, 平成26年度より, このような問題意識をもった自然科学系や社会科学系分野の研究者からなる学際的な研究チーム「水循環プロジェクト」を立ち上げ, 島嶼地域の水循環を総合的に理解する研究を推し進めるとともに, 行政や地域の方と一緒に学ぶワークショップを重ねてきました。平成29年度には, これらの取り組みが評価され, 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST)の平成29年度「科学技術コミュニケーション推進事業未来共創イノベーション活動支援」に「水の環でつなげる南の島のくらし」(代表 琉球大学 理学部 新城 竜一)プロジェクトとして, 採択されました。琉球大学の水循環プロジェクトチームを中心に, 地域の行政やNPO等の団体とともに協働・対話しながら, 私たちの住む島嶼地域の健全な水循環のあり方について考え, 実践していきます。
3.主な活動地域
沖縄県八重瀬町,宮古島市,多良間村
4.主な活動内容
自然共生社会の形成を目指し、共に学び、考え、実践するための「歯車」を設計し、それぞれが連動して回り続ける仕組みづくりを支援します。

1)科学的な知見を共有し、問題の背景や解決策について理解を深めます。
- 高度専門職員の育成
- 水循環ワークショップ
2)地域の多世代や多様な立場の方との対話をとおして、共に健全な水環境のあり方や、それぞれの立場から何ができるかを考えます。
- サイエンスカフェ
- 市民参加型アクションリサーチ
3)地域の方が地域の健全な水循環と文化を次世代に伝えるため「持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)」を実施するサポートをします。
- 南の島のESD教育カリキュラム・教材の開発
- 市民コミュニケーターの育成
- 大学博物館のビオトープを活用した水辺環境教育プログラムの開発